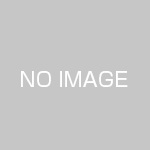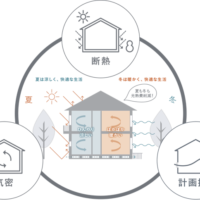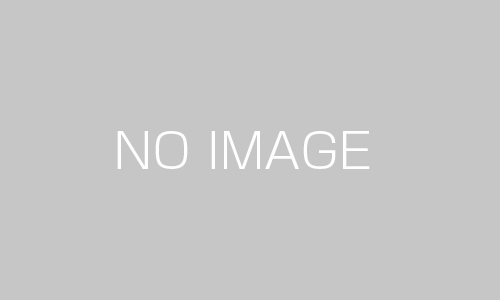建築費だけではない家づくりにかかるお金。建ってみれば予算オーバー。こんなことにならないためにも、どんな費用が必要か、その中身を知っておきましょう。
建築費だけではない家づくりにかかるお金。建ってみれば予算オーバー。こんなことにならないためにも、どんな費用が必要か、その中身を知っておきましょう。
\注文住宅を建てるならまずはカタログ請求から/
| 本体工事費 |
まず建築工事費としては、建築本体を建てるためにかかる本体工事費と、本体とは切りはなして考えることが多い別途工事費があります。また、実際に生活を始めるまでには建築費用のほかにもいろいろな諸費用がかかり、これらを合算したものが総費用になります。
通常、家を建てるのに必要な費用の内訳は、本体工事費が70~80%、別途工事費が15~20%、諸費用は5~10%ぐらいが目安となります。
まず、本体工事費の内訳ですが、
・仮設工事・基礎工事・躯体工事・木工事・屋根工事・板金工事・左官工事・内装工事・塗装工事・設備工事・電気工事・ガス工事・換気設備工事などで構成されますが、施工業者によって内訳や内容は変わってきますので、見積もりの際には内容の確認が必要です。
工事費の目安としてよく目にする表示金額や坪単価は、本体工事費を基準に考えられることが多いので、それだけに目を奪われると最終的に「予算が足りない」ということになりかねませんので注意が必要になります。
| 別途工事費 |
次に別途工事費ですが、これも生活をするためには欠かせない工事です。
・解体工事費(建て替えなどの場合)・屋外給排水、電気ガス工事・照明・カーテン工事・空調工事・エクステリア工事、地盤改良工事などがあげられますが、これらも施工業者によってその内容・内訳は変わってきます。最近よく見かける太陽光発電や蓄電池、これから導入例が増えてくるであろうエネファームなどの省エネ設備も、もちろん別途工事。設備を購入する費用だけでなく、設置のための補強が必要な場合がありますので、採用を検討する方は、当初プランから住宅会社とよく相談しておく方がいいでしょう。
設計費の取り扱いも業者によってさまざま。別費用として計上する場合もあれば、見積項目には上げず、建築工事費の中の諸経費に含まれる場合もあります。
| 建築費以外の諸経費 |
意外とかかるのが、この諸経費。工事請負契約書の印紙代や建築確認申請費、地鎮祭の費用や、敷地条件によっては敷地及び地盤の調査費、建て替えの場合は仮住まいの費用などがかかる場合があります。ほかにも、完成保証や地盤保証などの「保証」や、「住宅瑕疵担保履行法」に基づく「保険」といった費用もあり、住まいの安心を担保するのにも経費がかかります。
また、不動産業者を通じて土地を購入した場合、「不動産の価格×3%+6万円×1.1」といった仲介手数料も必要になります。
住宅ローンを組むのにも諸費用があります。印紙代、ローン手数料、抵当権設定登記料、所有権移転登記料、団体信用生命保険料、火災保険料、地震保険料、つなぎ融資にかかる利息などです。着工後にも上棟式の費用や大工さんへのお茶菓子代などや、入居までにはさらに、登記費用や不動産取得税、引っ越し費用や家具・家電製品の購入代などが必要です。
消費税率は10%です。土地については非課税ですが、建築費用はもちろん、業者に支払う仲介手数料にも土地・建物の区分に関わらず消費税がかかります。1つ1つは数万円でも、すべて合わせると100万円単位のお金に。
新しい生活を心から楽しむためにも、自分たちの予算をしっかり把握し、予算を守った家づくりを心掛けることが大切です。
| さまざまな税金 |
家づくりにかかる税金にもさまざまなものがあります。
印紙代 印紙代は、不動産売買や銀行からお金を借りるときの金銭消費貸借契約、住宅会社との工事請負契約などの契約を交わすときに課税されるもので、それぞれの契約書に、契約金額に応じた額の印紙を貼ることで納税する仕組みです。金額は借入や契約の額によって決まっています。
※不動産の売買契約書や工事請負契約書に関する印紙税については、令和9年3月31日まで軽減措置が施されています。
登録免許税 土地・建物を取得した時には、その不動産の権利関係を確定するために、法務局において土地についての所有権移転登記や建物についての所有権保存登記・所有権移転登記をします。この登記を行うときにかかるのが登録免許税です。税額は、登記の種類により課税標準と税率が決められています。個人が住宅を新築または取得した場合には、床面積井が50㎡以上であることや、新築または取得後1年以内の登記であることなどを条件に、令和9年3月31日まで税率が低くなる特例が設けられています。
※認定長期優良住宅では、令和9年3月31日までの措置として、保存登記が0.1%、所有権移転登記が0.2%優遇されています。
◎登録免許税の税率と軽減措置の特例(令和9年3月31日まで)
| 登記の種類 | 課税標準 | 通常の税率 | 軽減措置 |
| 家屋の所有権保存登記 | 固定資産税評価額 | 0.4% | 0.15% |
| 家屋の所有権移転登記 | 固定資産税評価額 | 2.0% | 0.3% |
| 抵当権の設定登記 | 債権金額 | 0.4% | 0.1% |
不動産取得税 不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県から課税される税金。計算の基となる課税標準額は、市町村の固定資産税台帳に登録された価格によることが原則です。土地及び住宅に関しては、税率が4%から3%に軽減される特例措置が令和9年3月31日まで延長されていますが、一定の要件を満たしたマイホームについては、課税標準額を減額する特例や税額の軽減措置がありますので、一般の住宅で土地面積が200㎡以下の場合には、実質的に不動産取得税がほとんどかかからないケースも多くなります。
◎住宅・住宅用土地についての不動産取得税の軽減(令和9年3月31日まで)
|
新築家屋 |
要件 | 一戸建て住宅/50㎡以上240㎡以下 |
| 軽減額 | 評価額から1200万円(長期優良住宅の場合には1300万円)を控除して税額を算出。税率を4%から3%に | |
|
住宅用地 |
要件 | 土地取得の日から特例適用住宅が新築されるまでの期間など、一定の要件を満たす敷地 |
| 軽減額 |
課税標準えお固定資産税評価額の1/2に。税率を4%から3%に。(1)45,000円(2)土地評価額の㎡単価×1/2×床面積の2倍(200㎡まで)×3/100 ※上記金額のいずれか高い方を税額から減額する |
固定資産税 マイホームを持つと、毎年その不動産が所在する市町村から固定資産税や都市計画税が課せられます。固定資産税は毎年1月1日現在の固定資産の所有者が納税義務者となり、毎年4月1日から始まる年度の税金を納付することになります。
都市計画税 都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に使われる目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税金です。両税とも、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となり、基準年度に評価替えが行なわれ、原則として3年間据え置かれます。この税につきましても、一定の要件を充たした住宅には、税額の軽減措置が講じられます。
家づくりの中でも、要といえるのが資金計画。30年35年と続く住宅ローンの返済を抱えるお金の問題は、まさに一生もの。
それぞれ異なるお財布事情を理解した上で、一緒に資金計画書の作成をしてくれる住宅会社を選ぶことが公開しない家づくりへの一歩かもしれませんね。
\ビオラホームへの来場予約はこちら/